学習するとき、どんな点に気をつけたらいいのか、場面ごとにポイントをまとめました。
①基礎知識の学習(ストラテジ系)
参考書の読み方(1回目)
〇時間をかけないで、気楽に読みます。
①今、読んでいる分野に、どんな用語があって、どこにまとめられているか?
②本で「ポイント!」あるいは「覚えるところ」など強調していることは、どこに書いているか?
〇最近のシラバスで変更になっている次の点が、どこに書いてあるか確認しておきましょう。
企業活動
①社会における IT 利活用の動向
(デジタルトランスフォーメーション(DX)などの部分)
②データ(ビッグデータを含む)を分析して利活用することによる、業務改善や問題解決の手法
(データサイエンス、ビッグデータ分析などの部分)
③売上と利益の公式、それを使った計算問題
ビジネスインダストリ
① AI 利活用の原則及び指針
(人間中心の AI 社会原則など)
② AI の活用領域及び活用目的
(AI による認識、AI による自動化など)
③ AI を利活用する上での留意事項
(データのバイアスなど)
④IoT を利用したシステム
(CASEなどIoTを利用したシステム例やそのしくみなどの部分)
⑤ロボットの利用例
(産業や医療などさまざまな分野での利用例の部分)
参考書の読み方(2回目)
〇読みながら、全体の内容について、用語や公式を覚えます。覚えておきたい内容を、アンダーラインで強調します。
- 用語の名称
- 特徴(類似したもの、技術との違い)
- 使う領域・場面での使い方
②重要用語の学習(ストラテジ系)
本サイトでは、各用語にシラバスのバージョン、シラバスの項目を付けました。
特に、Ver.4.0、Ver.5.0、Ver.6.0の用語は、過去問題が少ない用語なので、重点を置いて学習しましょう。
なお、シラ外の用語は、シラバスにありませんが、過去(公開)問題に出てきた用語なので、確認しておきましょう。
③新しい用語の学習(ストラテジ系)
どんな新しい用語があって、どんな点を暗記するとよいのか、他の用語との関係を知ってから学習すると効果が高まります。
④覚えたことの確認(ストラテジ系)
こまめに、覚えたことを繰り返して確認すると、長い時間覚えていられます。
分野別に確認すると効果的です。

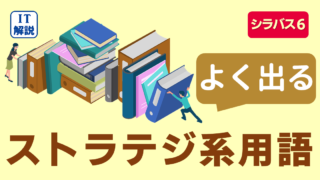
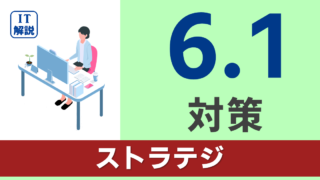
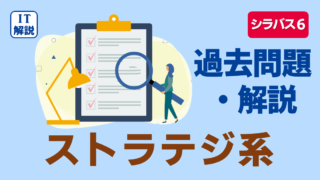



コメント